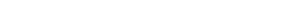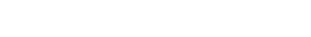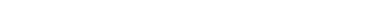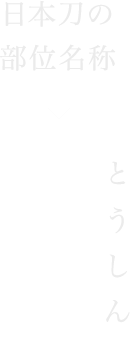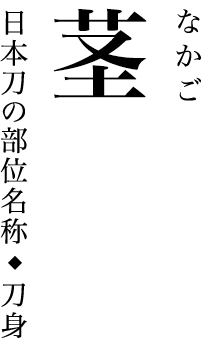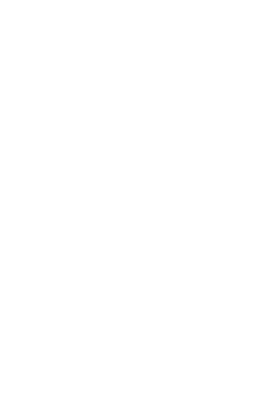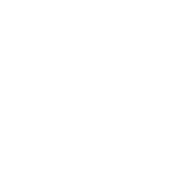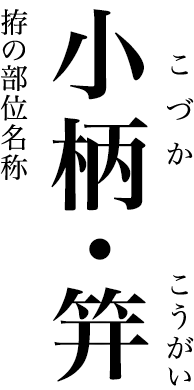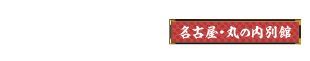
刀の部位名称を知ることは、解説文を読んだり、鑑賞した時の感想を相手に伝えたりするうえで非常に大切です。
実際の日本刀の写真を見ながら、部位を説明していきます。

![太刀 銘 直綱作(たち めい なおつなさく)[重要美術品/南北朝時代]](https://www.touken-collection-nagoya.jp/app/themes/wp-templ/knowledge-swords-photos/sword-structure/pc/image/img-section02.png)
![太刀 銘 直綱作(たち めい なおつなさく)[重要美術品/南北朝時代]](https://www.touken-collection-nagoya.jp/app/themes/wp-templ/knowledge-swords-photos/sword-structure/pc/image/img-section02-p.png)
[重要美術品/南北朝時代]
刀身の部位は、上身(かみ)と茎(なかご)に分けることができます。
このふたつを分けているのは、「区」(まち)と呼ばれる境界線で、ここに鎺(はばき)が取り付けられます。
棟(むね)側の区を棟区(むねまち)と呼び、棟区から鋒/切先(きっさき)まで線を引いて線と棟が一番離れている部分を「反り」(そり)の寸法として測ります。
刃長(はちょう)とは上身の部分の長さです。
刀身の幅を「身幅」(みはば)と言いますが、特に鋒/切先付近の幅を「先幅」(さきはば)、鎺付近の幅を「元幅」(もとはば)と言い、鑑賞の際にはここを比較することも多いです。
鋒/切先(きっさき)とは、刀身の最も先端にある部分のこと。
鋒/切先と物打ち(ものうち)の間にある線のことを「横手」(よこて:横手筋[よこてすじ])と言いますが、平造り(ひらづくり)の場合にはありません。なお、鋒/切先の刃文のことを「帽子」(ぼうし)と言います。
刀剣で実際に斬り付けるときに、最もよく切れる部分を物打ちと言い、先端から3寸(約9.1cm)ほど下にあります。
鎬造り(しのぎづくり)の刀剣の場合、上身は「鎬筋」(しのぎすじ)を境に鎬地(しのぎじ)と平地(ひらじ)に分けることができます。
鎬筋は、横手から茎の最下部まで続き、刃と棟の中間で、山高くなっている境界線のこと。
鎬筋と棟に囲まれた部分は鎬地と言います。
一方、鎬筋と刃の間の部分は平地と言います。
平地は地鉄(じがね)や刃文が見やすいです。
ちなみに、刃文の白い部分が鎬筋に近づくほど「焼きが高い」と表現し、焼きの高低には刀工の個性や時代の特徴が表れます。
茎は刀剣を鑑定する上では非常に重要な部位です。
茎の先端は「茎尻」(なかごじり)。剣先のように尖った「剣形」(けんぎょう)や、栗の尻のように丸みを帯びた「栗尻」(くりじり)など、様々な形状があり、時代や刀匠によって異なる特色がよく窺える箇所です。
茎には刀身が柄(つか)から脱落しにくくするために鑢(やすり)がかけられていますが、かける向きや形状によってさまざまに異なる鑢目(やすりめ)も、刀工を見極めるポイントとなります。
銘(めい)とは、刀剣の作者名や作刀年を刻んだ文字列のこと。
「鏨」(たがね)を打ち込んだ痕や銘の底に発生した錆などが鑑賞のポイント。
目釘穴(めくぎあな)とは、柄に「目釘」で茎を固定するために穿たれた穴。
時代の移り変わりによる変化や、磨上げ(すりあげ:刀剣の寸法を短くすること)によって開け直されたり、閉じられたりした場合があり、穴が複数になっている物も存在します。


勝虫図揃金具 陰蒔絵肥後拵 かちむしずそろいかなぐ かげまきえひごごしらえ
勝虫とはトンボ(蜻蛉)のこと。
トンボは前に向かって飛び、後ろに退くことがないことから、武士の間では縁起物の意匠として好まれてきました。
勝虫図で揃えられた本拵を見ながら、拵の部位・名称を学んでいきましょう。
手で握る部分は柄(つか)。柄には鮫皮を取り付けてその上に柄巻(つかまき)の紐を巻くことが多いです。
柄巻は、柄を革緒(かわお)や組紐などで巻き締めることで、柄を装飾するだけでなく、柄そのものの補強や手の滑り止めとしての効果も得られます。柄巻師(つかまきし)という職人による手仕事です。
頭(かしら)にも勝虫の意匠が施されます。
頭は柄の先端を補強し、縁(ふち)は刀の入れ口を補強する金具ですが、揃いの意匠とされることが多く、合わせて「縁頭」(ふちがしら)とも呼ばれます。
「つば迫り合い」という言葉で現代にも残っている「鍔」(つば)。
柄を握る手を守るだけでなく、刀の重心を調節する役割も。主に鉄製ですが、銅で作られている物もあります。
鍔の意匠は美術的にも評価され、コレクターも多く、世界中で愛好されています。
鞘は、ホコリや雨露から保護するために、刀身を収める部分。江戸時代に武士の正装として黒漆塗の鞘が定められましたが、鞘は黒漆だけでなく、朱漆、茶漆などの色もあり、金粉を使った金梨子地(きんなしじ)塗りや沃懸地(いかけじ)塗りなど、多様な表現が存在します。
本拵は黒漆塗ですが、勝虫の模様をうっすらとあしらっており、意匠性に富んでいます。

鞘の漆塗りでは、トンボの羽の網目模様(翅脈:しみゃく)までこまかく表現されている。

鞘の先端(鞘尻)を守る金具が鐺(こじり)。必ずしもこれが付けられているとは限りません。ハートマークのような模様は「猪の目」(いのめ)であり、これも縁起物。
細工や雑用などに用いられた小刀用の柄が「小柄」(こづか)です。打刀拵の差裏に収納され、非常時などには手裏剣のように投げ打つなどして用いられることもあったそうです。
「笄」(こうがい)は、髪の乱れを直したり、髷(まげ)の中の痒いところを掻いたりするなど、身だしなみのための小道具。
本拵に付属する小柄・笄は後藤光晃の銘が切られています。
小柄・笄・目貫(めぬき)の3点をそろえたものは「三所物」(みところもの)として尊ばれています。