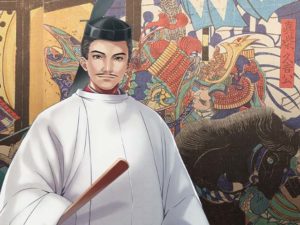「小牧・長久手の戦い」とは、「豊臣秀吉」が「織田信長」の後継者としての地位をかけて、「織田信雄」(おだのぶかつ:織田信長の次男)・「徳川家康」連合軍と対決した戦いです。豊臣秀吉と徳川家康が直接対決したのは、この戦いが最初で最後。本当に強かったのはどちらだったのかと多くの歴史ファンを今でも虜にしています。小牧・長久手の戦いが描かれた浮世絵をご紹介しながら、気になる勝敗などについて、詳しく解説します。
「小牧・長久手の戦い」とは、1584年(天正12年)に、小牧(現在の愛知県小牧市)と長久手(現在の愛知県長久手市)を主戦場として展開された、「豊臣秀吉」対「織田信雄」・「徳川家康」連合軍の戦いのことです。
「織田信長」の死後、豊臣秀吉は、謀反を起こした「明智光秀」を「山崎の戦い」で破り、清洲会議では織田信長の長男「織田信忠」の遺児「三法師」(織田秀信)を織田信長の継嗣に推挙。織田信長の三男「織田信孝」を推していた「柴田勝家」を「賤ケ岳の戦い」で破り、さらに織田信孝を自刃へと追い込みました。
また、織田信長の後継者としての地位を確立するため、織田信長の次男・織田信雄を排除しようとしていたのです。豊臣秀吉は、まず織田信雄の家老「津川義冬」、「岡田重孝」、「浅井長時」の3人を手懐け、機をうかがっていました。
しかし、これに気付いた織田信雄は3人の家老を豊臣秀吉と内通していた罪で誅殺。これに怒った豊臣秀吉が、織田信雄を追討するために起こしたのが、小牧・長久手の戦いだったのです。
「楊洲周延」(ようしゅうちかのぶ)は、1838年(天保9年)生まれ。歌川国芳、歌川豊国(三代)、豊原国周に師事し、江戸時代末期から明治時代にかけて活躍した浮世絵師です。
自ら「彰義隊」の隊士として参戦した異色の浮世絵師。明治時代になると、武者絵や美人画で成功し、小牧・長久手の戦いの絵も数多く描きました。
「小牧山戦争之図」は、色鮮やかで美しく、勇ましい戦争絵です。画面右側には豊臣秀吉軍、画面左側には徳川家康・織田信雄連合軍が描かれています。中央にいるのは、豊臣秀吉の重臣「加藤清正」で、愛刀「片鎌槍」を振り回しているところ。
一方、対抗しているのは徳川家康の重臣「本多忠勝」で、愛刀「蜻蛉切」を握っています。加藤清正は、豊臣秀吉の子飼いで重臣。本多忠勝は、徳川四天王のひとりとして徳川家に仕え、生涯57回の戦に出陣し、一度も負けたことがないという猛者中の猛者でした。
両者とも槍の達人として知られており、まさに実力に過不足がない好敵手。しかし、実際には、小牧の戦いにおいて、小牧山城周辺でこのような戦が行われた史実はありません。両軍とも本陣から動かず、にらみ合いを続けたのです。

楊洲周延 作「小牧山戦争之図」(所蔵:刀剣ワールド財団)
「小牧山二康政秀吉ヲ追フ」は、「榊原康政」が豊臣秀吉を猛追している場面です。榊原康政は、徳川家康の重臣で徳川四天王のひとり。小牧・長久手の戦いでは、豊臣秀吉側の「森長可」(もりながよし:森蘭丸の兄)、「池田恒興」(いけだつねおき:大垣城[岐阜県大垣市]の城主)を討ち取るなど活躍しました。
さらに、豊臣秀吉を非難する「檄文」(げきぶん)を送ったことでも有名です。豊臣秀吉は怒り狂い、榊原康政の首に10万石の懸賞金を掛けたほどでした。
こちらの場面も史実にはありませんが、檄文を送った榊原康政の心の内をよく表現していると言えます。榊原康政の勇猛ぶりがよく伝わる、楊洲周延らしい美しいタッチの1枚です。

楊洲周延 作「小牧山二康政秀吉ヲ追フ」(所蔵:刀剣ワールド財団)
「小牧役 加藤清正 本多忠勝」は、豊臣秀吉軍加藤清正と徳川家康・織田信雄連合軍本多忠勝との一騎打ちの様子が描かれた、壮麗で迫力のある3枚絵です。
画面右で細長い「長烏帽子形兜」(ながえぼしなりかぶと)を身に着け、愛刀・片鎌槍を握っているのが加藤清正。一方、鹿の角をイメージした「鹿角脇立兜」(かづのわきだてかぶと)を被り、愛刀・蜻蛉槍を握っているのが、本多忠勝です。
残念ながら、この一騎打ちも史実にはありません。強者ふたりの対決を見てみたかった、楊洲周延の願望が表れた絵だと言えるのです。

楊洲周延 作「小牧役 加藤清正 本多忠勝」(所蔵:刀剣ワールド財団)

小牧山城・楽田城から長久手、岡崎城
までの距離(長久手の戦い)
膠着状態が続いた小牧の戦いですが、先にしびれを切らしたのは、豊臣秀吉軍でした。豊臣秀吉軍は、徳川家康が小牧山城に留まっているうちに、警備が手薄となった徳川家康の居城・岡崎城(愛知県岡崎市)を攻撃してしまおうと動いたのです。
しかし、その作戦は徳川家康・織田信雄連合軍に漏洩し、長久手の地で挟み撃ちに。この結果、豊臣秀吉軍は2,500兵が戦死して撤退。徳川家康・織田信雄連合軍が実質的に勝利しました。
これが、「長久手の戦い」です。ところが、織田信雄は豊臣秀吉に面会を求められて承諾。徳川家康に相談もなく、単独で和解に応じたのです。
これにより、豊臣秀吉は、政治的に勝利。この一件で、豊臣秀吉は天下統一への道が拓かれますが、徳川家康に対して恐れを持つようになるのです。
「歌川芳虎」は、生年不詳ですが、歌川国芳に師事し、1830年(天保元年)から1887年(明治20年)頃にかけて活躍した浮世絵師です。
諷刺精神に長け、徳川家康を風刺した錦絵「道外武者御代の若餅」を描き、手鎖50日の処罰を受けたことでも有名。武者絵、役者絵の大首絵、開化絵に優れ、人気となりました。
「二雄槍戦之図」に描かれているのは、豊臣秀吉軍・加藤清正(この絵では佐藤虎之介正清)と徳川家康・織田信雄連合軍の本多忠勝(この絵では紺田瓶八郎貞数)による一騎打ちの様子です。ふたりの武将が勇猛優美で、明るく華やかに描かれています。
本浮世絵が描かれたのは、1866年(慶応2年)。1804年(文化元年)から1878年(明治11年)まで、徳川家及び大名家を描くことは法令で禁止されていたため、偽の名前で描く「偽名絵」(にせなえ)という手法が取られています。
この絵も史実ではありません。史実では、小牧山城で留守を任されていた本多忠勝が500兵を引き連れて、小牧から長久手へ向かうと、その姿を見て、豊臣秀吉軍は撤退したと伝えられています。加藤清正は、豊臣秀吉軍の殿(しんがり:撤退の最後尾部隊)を務めていたのです。

歌川芳虎 作「二雄槍戦之図」(所蔵:刀剣ワールド財団)
「水野年方」(みずのとしかた)は、1866年(慶応2年)生まれ。明治時代初期から中期にかけて活躍した浮世絵師。14歳で月岡芳年に入門して歌川派の浮世絵を学び、そのあと、柴田芳洲に南画、渡辺省亭に花鳥画を師事しました。穏やかで上品な作風に定評があり、浮世絵、風俗画の地位向上に貢献したのです。
「本多忠勝小牧山軍功図」に描かれているのは、本多忠勝が戦場を見定めながら、馬に水を飲ませている場面です。戦前とは思えない、とても静寂で穏やかな雰囲気。
当初、本多忠勝は小牧山で留守役を任されていましたが、急遽、500兵を引き連れて長久手の戦いに加勢。500m先に豊臣秀吉軍を見付けると、一旦、単騎で近くの川へ行き、馬に水を飲ませるという行動にでたと言われています。
本多忠勝と言えば、一度も戦に負けたことがない、かすり傷さえ負ったことがないという男。あまりにも悠然としている本多忠勝の姿を見付けた豊臣秀吉軍は戦慄し、撤退を決めたと伝えられているのです。

水野年方 作「本多忠勝小牧山軍功図」(所蔵:刀剣ワールド財団)