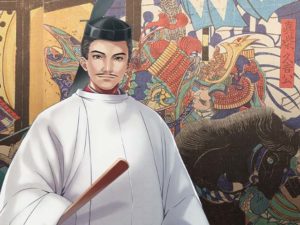「矢作橋」(やはぎばし)とは、愛知県岡崎市にある「岡崎城」のすぐ近くに架かっている橋のことです。岡崎城は江戸幕府初代将軍「徳川家康」が生誕した城で、城下町が栄え、矢作橋は交通の要路となり、多くの人々が往来しました。「旅」がブームとなった江戸時代後期には、一度は訪れてみたい場所として憧れられたのです。矢作橋が描かれた浮世絵について、詳しくご紹介します。
「矢作橋」(やはぎばし)とは、愛知県の西部、岡崎市矢作に存在する橋のことです。
「矢作」(やはぎ)とは地名で、古き英雄「日本武尊」(やまとたけるのみこと:12代天皇「景行天皇」の皇子)が、東征(とうせい:東方の敵の征伐)の際に、この地で自生する良い竹を見付けて、部民に10,000本の矢を作らせたことに由来しています。
また、矢に羽を付けることを「矧ぐ」(はぐ)と言うことから、「矢矧」の文字も使用されました。この矢作にある橋だから矢作橋。
他にも、「矢作川」(長野県を源流に、岡崎平野を経て、愛知県の三河湾に流入する全長117kmの一級河川)や「矢作神社」も、同じ由来で有名です。
江戸時代の矢作橋の長さは、208間(約347m)。当時は、日本一長いと謳われた橋で、交通の要路としてたいへん栄えました。
現在の矢作橋の長さは300mで少し短くなりましたが、矢作橋には国道1号線が通り、岡崎市矢作は愛知県の中核地として賑わっています。


「葛飾北斎」(かつしかほくさい)は、1760年(宝暦10年)生まれ。6歳の頃から物の形状を写すほど絵が好きで、19歳でトップ浮世絵師「勝川春章」に入門。翌年デビューして活躍します。
1814年(文化11年)に発表した「北斎漫画」が注目され、1830年(天保元年)に発表した「富嶽三十六景」で風景画家としての地位を確立しました。「諸国名橋奇覧」、「諸国滝廻り」も注目されています。
「諸国名橋奇覧 東海道岡崎矢はぎのはし」は、1833年(天保4年)に、葛飾北斎が全国の珍しい橋をモチーフに描いたシリーズ絵です。「東海道岡崎矢はぎのはし」は、矢作橋のこと。全長は347mという長さで、日本最大の橋と持て囃されました。
本浮世絵は、アーチ状の大きな橋の上に大勢の人々が行き交い、橋の下には城下街や武士が弓術を行う様子、色とりどりの傘が干される様子が描かれ、とても和やかです。
当時の矢作橋は木造の橋だったとのことですが、実際にはこんなに大曲してはなかったよう。タイトルの「奇覧」とは葛飾北斎の造語です。葛飾北斎の感性で、奇しい大きな橋として描かれ、話題となりました。

葛飾北斎 作「諸国名橋奇覧 東海道岡崎矢はぎのはし」(所蔵:刀剣ワールド財団)
「歌川広重」(うたがわひろしげ)は、1797年(寛政9年)生まれ。本名は安藤なので、安藤広重とも呼ばれています。「歌川豊広」に師事し、はじめは美人画や役者絵を描いていましたが、葛飾北斎に憧れて風景画に転向。
1833年(天保4年)に「東海道五十三次」を発表すると、葛飾北斎を凌ぐほど人気となり、風景画家としての地位を確立しました。
「東海道五十三次 岡崎 矢矧之橋」には、当時、日本一の長さを誇った矢作橋を大名行列が通行しているところが描かれています。
華やかな駕籠(かご)に乗った大名が大勢の家臣に守られて移動し、薙刀を担ぐ人や対挟箱を運ぶ人、お坊さんの姿もあり、賑やかです。
透視画法(遠近法)が用いられ、遠くには岡崎城がそびえています。東海道五十三次とは、日本橋から京都三条までの東海道筋に設けられた宿場のことです。
本浮世絵は、シリーズ絵の中の1枚。岡崎は、徳川家康の生家岡崎城がある宿場町で、徳川家康が居住していた「駿府城」がある府中(現在の静岡県静岡市)に次ぐ規模を誇っていました。この東海道五十三次が空前の大ヒット。
歌川広重の絵は実際に見る風景に近いのが良いところです。天才的な構図で描く葛飾北斎よりも真実味があり、旅行本として好まれました。

歌川広重 作 「東海道五十三次 岡崎 矢矧之橋」(所蔵:刀剣ワールド財団)
「月岡芳年」(つきおかよしとし)は1839年(天保10年)生まれ。12歳のときに「歌川国芳」に師事し、武者絵や役者絵、血みどろ絵を描きました。「豊臣昇進録」が描かれたのは、1868年(明治元年)頃。
同年5月に起こった「上野戦争」を取材して血みどろ絵を描き、そのあと、神経衰弱に陥ってしまうのですが、こちらはその前に描かれた貴重な作品です。
本浮世絵は、「豊臣秀吉」の生涯を描いた豊臣昇進録というシリーズ絵の中の1枚です。「中村猿之介」(豊臣秀吉)と「蜂須賀正勝」(はちすかまさかつ:通称・小六)が矢作橋ではじめて出会うところが描かれています。
登場する武士の表情が豊かで、衣装も華やか。奉公先から逃げた幼い豊臣秀吉は、実家に帰ることもできずに矢作橋で野宿していると、蜂須賀村(現在の愛知県あま市)の土豪蜂須賀正勝に頭を蹴られます。
豊臣秀吉が怒って蜂須賀正勝の槍の柄を掴んで文句を言ったところ、度胸があると見込まれ、子分にしてもらえたというお話。
のちにこの立場は逆転し、蜂須賀正勝は与力となって豊臣秀吉を支えることになります。矢作橋は歴史的な場所として登場するほど、昔から有名な橋だったことが分かるのです。

月岡芳年 作「豊臣昇進録」(所蔵:刀剣ワールド財団)
「山崎年信」は、1857年(安政4年)生まれ。13歳で月岡芳年に入門し、「月岡四天王」のひとりと呼ばれ、将来を有望視されていました。「太閤実記雪月花之内矢矧之月」を描いたのは、1879年(明治12年)。
しかし、1880年(明治13年)以降は、酒に溺れて仕事に支障をきたすようになり、1882年(明治15年)には、月岡芳年のもとを去ります。そのあと、新聞挿絵を認められたものの、肺炎になり、29歳の若さで早世してしまうのです。
太閤実記雪月花之内矢矧之月も、「日吉丸」(豊臣秀吉)と「蜂須賀小六」(はちすかころく)が矢作橋ではじめて出会ったときのことを描いた武将浮世絵です。
丸く美しい満月の夜に、無防備な姿で眠っている日吉丸。その姿をのぞき込んでいるのは、蜂須賀小六の家老「稲田大炊」(稲田植元)。その後ろには、蜂須賀小六一行が並んでいます。
蜂須賀小六と稲田大炊は、のちに豊臣秀吉を補佐する人物。このふたりに出会ったことで日吉丸は夢のようにどんどん出世し、豊臣秀吉として天下統一を果たしたのです。まさに丸い月がツキを呼ぶ、幻想的で縁起の良い1枚です。

山崎年信 作「太閤実記雪月花之内矢矧之月」(所蔵:刀剣ワールド財団)